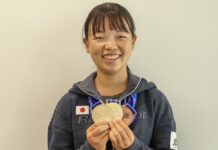新型コロナウイルスの影響によるオンライン講義に、視覚障がいを持つ学生はアクセス困難という思わぬ事態が起きていた。オンライン講義はパソコン画面上の複雑な操作が必要となり、講義内容もプレゼンテーションスライドや文字を画面に表示しての説明が増え、視覚に頼る部分が多くなるためだ。一方で、精神的な障がいを持つ学生にとっては、他者との直接的なコミュニケーションが減り、授業参加のハードルが低くなるといったオンライン講義の思わぬ利点もあった。専修大学障がい学生支援室は、オンライン講義に戸惑う多様な特性を抱える学生たちへの対応と、学内全体に障がいへの理解を広めるために奔走する。
パソコンからスマホへ、操作手順減らす
オンライン講義で初めに浮上したのが、目が見えない学生へのサポートだった。身体、精神の両分野で障がい学生を支援する同支援室のスタッフのうち、視覚、聴覚の制限や肢体の不自由など身体的な障がいを主に担当する若月麗さんは、「目が見えない学生は画面上のどこにどんなボタンがあるか把握できず、いくつもボタンを押す工程を踏み複雑な操作をしなければいけないため、パソコンでインターネットサイト上からGoogleクラスルームに入ることも困難だった。緊急事態宣言下で直接会うことも出来なかったため学生と電話を繋いで、2、3時間かけてできること、できないことをとひとつずつ確認していった」と振り返った。
試行錯誤した結果、パソコンでアクセスすることを諦め、携帯電話にGoogleクラスルームやmeetを個別にアプリとしてインストールし、操作がアプリを立ち上げてボタンを数回押すだけとなったことで解決された。

「点字ディスプレイ」が強い味方に
次に立ちはだかったのが、オンライン講義に音声だけでついていけるのかという問題だった。若月さんによると、パワーポイントのスライドや、文字を画面に表示しての説明が多いオンライン講義の場合、障がいのない学生は教員の声と画面に表示される文字テキストを同時に理解できる。だが目の見えない学生は音声だけで内容を理解しなければいけない。そこで活用されたのが、点字の凹凸を次々に作り出す「点字ディスプレイ」を備えた装置「ブレイルセンス」だ。あらかじめ用意した授業内容のテキストデータ(文字情報)を読み込ませることで、教科書やスライドの内容など、音声以外の情報を点字でつかむことができる。指定教科書を発行している出版社にテキストデータを提供してもらえるか掛け合ったり、担当教員に講義内容や課題情報をテキストデータで送ってもらうことをお願いすると若月さんは説明する。
これらの事前準備には、前年度から動き出すことが必要不可欠だ。しかし交渉先とやり取りが円滑に進まない場合は、支援が間に合わないという場面もある。その場合、学生本人が教員とメールで交渉し、テキストデータを多くもらって学習するというような措置で対応する。障がい学生自身、大学に通うと決めた時点で、多少の不都合やアクシデントなどは承知しているため、臨機応変に自ら解決に向けて動くことも多いという。
逆に、精神的な障がいがある学生にとって、オンライン講義には利点もあった。障がい学生支援室スタッフで臨床心理士の青木光信さんによると、対人緊張を持つ学生の場合、他の学生や教員とのやりとりがオンラインになったため緊張度合いが減った。講義への要望などもメールでなら以前よりうまく言葉にすることができた。また、人の顔と名前を一致させることが障がいのため難しい学生の場合、オンライン講義ではパソコン画面上に名前が表示されるためスムーズにコミュニケーションがとれたという声もあったという。
理解を広めるための支援室—コロナ機に新しい教育を
「『そういう人もいるよね』が(心の)片隅にあるだけで、授業の形だって友達の輪の形だって変わっていく」。若月さんは障害に対する意識をそう語った。今までの教育は学校に時間通りに来て、決められた場所で授業を受け、教員に提示された範囲の内容を網羅するというような、教える側の意図に合わせて学ぶことが基本だった。しかしコロナウイルス蔓延による影響で、学校に行けない人はオンラインで授業を受けられる。緊急事態での異例な対応だが、障がいへの理解が進めば、重度の発達障害のため、他人との接触による息苦しさで、他学生と同じ教室で授業を受けづらい学生が普段から別室で講義を受けられるようになる可能性も開けた。さらに、障がいある学生の学びを支援する学生「ピアサポーター」が本人に代わってノートを取るなど、もっといろいろなかたちで学習の場が提供される必要性を、今一番強く感じるという。

青木さんは、「障がいへの理解を広めることが私たちの仕事でもあるが、理解が広まり、世の中の人が障がいのある人に勝手に支援を行うことができるようになったたならば、この部屋(障がい学生支援室)はいらない」と話した。
障がいに対する「合理的配慮」というキーワードがよく用いられる。一方若月さんにとっては、「配慮」という言葉を聞くと必要以上に気を遣うように響いたり、何かを「やってあげる」という印象を抱いたりするため、「合理的調整」という言葉のほうが自らの考えや支援の形として「しっくりくる」という。
「初めて支援系の仕事に就いたとき、何かを『してあげよう』など思うことはおこがましいと思った。背中を少し支えて本人が自立していくようにすることが支援だと実感した」。ひきこもりやニートの復職を支援するNPO法人での勤務など、長年支援の仕事を続けてきた青木さんは、穏やかな笑顔でそう打ち明けた。
誰もが特性を抱える 「生き抜く」ための障がい学生支援
「『障がい』と形容されるか否かは、その特性が日常生活に支障をきたすと判断されるかということだけであり、私たちは誰もが様々な特性を持って生きている」。若月さんと青木さんは会話の節々でこの考えを繰り返した。さまざまな特性が現代の医療では「障がい」と認められる機会も増え、専修大学の障がい学生登録者は去年の33名から、今年は50名以上に増加している。
「障がいを持っているからといってその困難をなにもかも取り除くというわけではない」。そう若月さんは障がい学生の支援の意義について言う。「80歳まで生きるとしてこの後何十年間を自分でちゃんと生きていく力を大学4年間で身に着けて欲しい。それは障がいのある学生もない学生も変わりはない。ただ勉強や対人関係など、障がいのない学生が当たり前に行うことを、障害があることによって行えない、更に理解も得られない—といった最悪な状況にならないよう周知することや、障がいによって物理的にアクセスすることができない部分へのサポートを続けていきたい」