「ひとり親世帯」が置かれる状況が、新型コロナウイルス禍でより深刻になった。支援団体が行う食料配布会に並んだ女性は、コロナ禍で飲食店を解雇され、子どもが保育園を退園せざるを得ない状況になったという。親族など周囲に頼れない環境にコロナ禍も重なり、求職活動がままならず「今はほとんど収入がない」。保育認定の延長や再認定など、コロナ禍で各自治体に求められていた「柔軟な対応」が受けられていなかった可能性もある。一方、セーフティーネットであるはずの生活保護には「親族に知られてしまうかもしれない」と手が出せずにいる状況も明かした。
「勤務時間短く『使いづらい人』からクビ」
東京都庁前では毎週、支援団体が無料の食料配布会を開いている。食料を受け取ろうと列に並ぶ人は新型コロナウイルス禍が長引くにつれて増えている。
まだ寒さが残っていた1月下旬。2人の娘を連れた女性(32)が、家庭内暴力が原因で離婚後、元夫から身を隠しているため名前や居住自治体を伏せることを条件に取材に応じた。離婚したのは数年前で、今は「ひとり親」となった女性は、未就学の娘2人を横に、「上の子はちょうど反抗期なんです」と笑う。昨年末、知り合いから食料配布をしている場所があると教えてもらい、この場所にたどり着いた。元日に行われた配布会にも並んだ。
女性は飲食店でパート勤務していた。娘を保育園に送迎する必要があるなど働ける時間は短く、フルタイムでの勤務が難しいからだ。娘が体調を崩して園への迎えが突然必要になることもあったといい、子どもに生活を左右される「ひとり親」の厳しさがうかがえる。そうした状況のなか、新型コロナの感染が広がり始めた2020年春、女性はこの飲食店を解雇された。「私のような、勤務時間が短い『使いづらい人』からクビにされてしまった」。女性は肩をすぼめながら、当時を思い出した。
か弱い声「ポイントの戦いに負けた…」
「ひとり親」である女性の「失業」は、娘の保育園退園にも繋がった。
認可保育園では、幼稚園や無認可保育園と比べて保育料が安い一方、保育を必要とする子供を預かる制度であるため、就業を条件に入園できた場合、保護者が職をなくすと基本的に子供は入園条件を満たさなくなる。女性の娘を通わせていた関東地方の認可保育園でも同様だったという。入園条件には、一定時間の就業のほか、親族の介護、精神・身体障がいであることなどがある。
一定時間の就業が入園条件だった人が職をなくした後「求職活動」を条件に保育園に通うこともできるが、その期間は多くの自治体で「90日以内」となっている。その期間が過ぎても、必要であると認められれば「再度認定することも可能」(2014年9月の内閣府文書)とされている。そのため、女性は園側にコロナ禍で失業した事情を話したが、入園を希望しながら順番を待つ「待機児童」が発生していると説明され、退園が決まってしまったという。女性は、保護者の就労状況などの点数化によって入園可否を選考されることに触れながら、「ポイント制の戦いに、私の場合は負けてしまったんです」と、か弱い声で振り返った。
保育入園、長期求職者対応を国は求めたが
厚生労働省と内閣府は2020年6月、新型コロナによる求職活動の長期化に対応するため、求職活動を理由にした認定の有効期限を延長させたり、積極的に再度認定させたりすることなどを例として挙げ、「柔軟な対応」をするよう各自治体に求めていた。
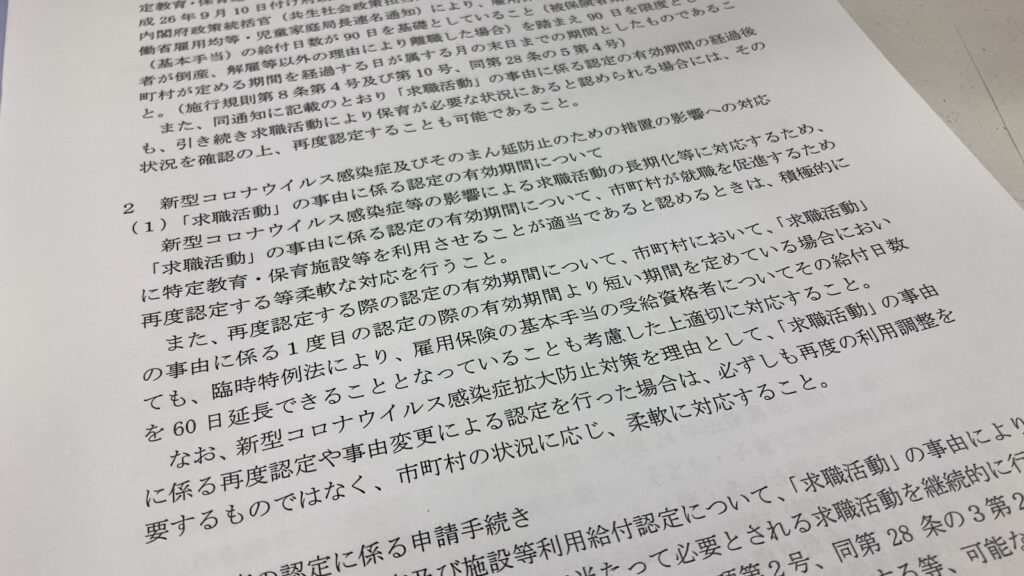
これについて、VIRIDISの取材に答えた内閣府子ども・子育て本部の藤原智史・参事官補佐は、「制度の変更などではなく、既存の制度の内容を改めてお伝えしているものになる。コロナ禍で困っている方に対して『柔軟な対応で配慮してください』ということ」と説明。認定については「各自治体が大きな裁量を持っている分野」で、「自治体が用意しているさまざまな制度を重層的に使いながら対応している、と聞いている」と話した。
この文書で求めた認定の有効期限延長や積極的な再度認定といった「柔軟な対応」がなされないことがあるかについては、「可能性としてありえないことではない」としつつ、実際の状況や(窓口である)自治体の認識を「確認しないことにはなんとも言えない」とし、今回のケースについての具体的な判断は避けた。
その上で、「入園の優先順位付けする点数については自治体の事情によって異なり、待機児童がいる自治体では(園に)入れない子どもがいるのは確かではある。ただ、働いている「ひとり親」で、かつ周囲に子どもの面倒を見られる親族等がいない状況であれば、(入園の)優先度が高いのが普通だと思う」と付け加えた。
「気づかれてしまうかも」 ためらい招く扶養照会
「周りは、見ていないようで見ていて怖い。だから、手が出せないんです」。
記者がコロナ禍で生活保護などの公的制度を利用したか聞くと、女性はそう答えた。周囲から生活保護の受給を勧められることもあるというが、「親族に気づかれてしまうかもしれない」と思い、受給申請に踏み出せていない。
生活保護法では、同居する親族などからの経済的支援を優先するよう定められている。審査では原則として、申請者への援助ができるか親類などに確認する「扶養照会」が行われることになる。例外は「扶養義務履行が期待できない者」(厚労省通知)と判断された親類に限られる。
「DVや虐待などの問題で援助を得られないから困窮する状況もあるので、親族に連絡されるかもしれないとなると申請をためらう人は残念ながら多い」と指摘するのは、生活困窮者の支援に取り組む認定NPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」の大西連理事長だ。
制度改善後も「ハードルなお」と識者
一般社団法人「つくろい東京ファンド」が20〜21年の年末年始、都内で開いた支援会場で相談に来た165人に聞き取り調査では、その時点で生活保護を利用していない128人のうち44人(34・4%)が、「(生活保護を)利用していないのは、家族に知られるのが嫌だから」と回答。「親族に知られないのなら(生活保護を)利用したい」と答えた人は51人(39・8%)に上り、扶養照会が困窮している人にとっての「ハードル」になっている。

支援団体などからの長年の指摘を受け、厚生労働省は21年2月、これまでは照会不要の目安として「20年間音信不通の親族」としていたものを「10年程度」に改正。また、照会しない場合として、▽親族が高齢や未成年▽家庭内暴力(DV)を受けた場合――と例示していたものに、新たに▽本人が親族に借金を重ねている▽相続をめぐり対立している▽縁が切られ関係が著しく悪い場合――なども加えた。
この改正について、大西氏は「(照会する)自治体の手間も省け、生活保護を受けたい人にとっても不要な扶養照会が減ることは良いことだと思う」としながらも、「(扶養照会の)制度自体は残っており、生活保護をためらわせる作用がなくなったわけではない。支援を受けるときのハードルになってしまうと、権利としての(生活保護)制度が活用されない状況につながる」と訴える。
さらに、「(扶養照会は)制度が改正されても慣習のように行われたり、自治体職員の『家族は養い合うべきだ』という悪意のない感覚から行われたりすることもある。制度はもちろん変わるべきだが、制度だけが変わっても現場で利用されなければ意味がない。だからこそ、社会の価値観ごと変わっていく必要があると思う」と強調した。
「手を差し伸べる側に、いつか私も」
「今は貯金を切り崩しながら生活するしかない」。女性と娘たちが暮らす部屋の家賃は「5〜6万円」(女性)。失業してほとんど収入がなくなっても毎月の支払いは迫る。そうした生活を打開するために、高報酬と言われている承認前の薬の安全性などを調べる「治験」を試してみたいと考えているという。治験にリスクがあることを記者が伝えても、「私は治験でもして、社会の役に立つくらいでしか(お金を)稼げないから」と続けた。
女性の頭には、昨年末に新宿・歌舞伎町で9歳の息子をホテルの高層階から転落させたとして母親が逮捕された事件が浮かぶ。女性は、「私には、そんな怖いことできないけれど」と語りながらも、「コロナ禍で、人の心がささくれてしまっているのかもしれない」と逮捕された母親の心情に寄り添った。転落階には男児のものとみられる靴が一足のこされていたという報道を目にしたといい、亡くなった男児を思い、声を詰まらせ、目にはうっすら涙を浮かべた。
食料配布に初めて行くのは、当初「おっかなびっくりだった」。でも、この事件を機に「娘たちにお腹を空かせるよりは」と改めて思い、足を運ぶことにしたという。
この食料配布会では、自らが受け取った食料の一部を、より多くの食料を必要としていそうな人に分ける様子がよく見られる。女性も、娘たちと一緒に列に並んでいると、何人もの人から善意で分けてもらっていた。「今の状況がすぐに良くなるとは思えない。けれど、私もいつかは手を差し伸べる側になりたいなって思っています」。女性はそう話し終えると、2人の娘とともにこの場所を後にした。



